
- HOME
- 化粧品OEMラボ
 肌の赤みや刺激を防ぎたいというニーズが高まる中で、化粧品開発の現場では「抗炎症」というキーワードが再び注目されています。マスク生活や環境ストレスにより肌バリアが乱れやすくなった今、単なる“敏感肌対応”を超えた機能設計が求められています。
肌の赤みや刺激を防ぎたいというニーズが高まる中で、化粧品開発の現場では「抗炎症」というキーワードが再び注目されています。マスク生活や環境ストレスにより肌バリアが乱れやすくなった今、単なる“敏感肌対応”を超えた機能設計が求められています。
市場では、ナイアシンアミドやツボクサエキスなど科学的エビデンスを持つ成分への関心が急上昇しており、矢野経済研究所の調査でも敏感肌化粧品市場は前年比5.6%増と拡大傾向を示しています。
参考:敏感肌化粧品市場に関する調査を実施(2025年) | 矢野経済研究所
こうした流れは、製品の安全性や信頼性を支える「抗炎症処方」を軸にブランド価値を再定義する好機といえます。炎症の抑制とバリア修復を両立させる技術開発はもちろん、医薬部外品承認や広告表現の適正化、スピーディなOEM展開など、研究開発からマーケティングまで一貫した戦略設計が鍵となります。
マスク生活や環境ストレスの増大によって、肌のゆらぎを感じる人が増加しています。これに伴い、敏感肌対応をうたう化粧品の市場は拡大を続けています。矢野経済研究所の推計によると、2024年度の国内敏感肌化粧品市場は前年度比5.6%増の1,010億円に達する見込みです。従来は一部の敏感肌層を対象としていた製品群が、いまや一般消費者にも広く受け入れられるようになりました。こうした市場の成熟は、「抗炎症」という観点から処方設計を見直し、ブランドの価値を再構築する絶好のタイミングをもたらしています。
次に、なぜ抗炎症スキンケアが注目されるようになったのか、その背景と科学的な位置付けについて整理していきます。
マスクの着脱や外的環境の変化によって、肌トラブルが顕在化するケースが増えました。赤み、刺激、乾燥などの悩みに対して「炎症を抑えるケア」を求める声が高まり、成分の選択や処方の設計においても抗炎症機能が重要視されています。特に、グリチルリチン酸やCICA(ツボクサエキス)、ナイアシンアミドなど、肌の鎮静や炎症抑制を裏付けるデータを持つ成分が注目を集めています。
近年では、化粧品の有効性や安全性を科学的根拠に基づいて示すことが求められています。展示会や業界セミナーのレポートでも、エビデンスベースでの成分訴求や低刺激・サステナブル対応を兼ね備えた製品が、差別化のカギになると強調されています。こうした動向を踏まえると、抗炎症というテーマは一時的なトレンドではなく、今後のスキンケア開発の中核となる価値軸として定着していくと考えられます。
このように、抗炎症スキンケアの注目は単なる消費者のニーズ拡大にとどまらず、研究・開発・ブランド戦略のすべての領域に影響を及ぼしています。
抗炎症とは、外的刺激によって誘発される炎症反応を抑制し、肌本来の恒常性を保つ働きを指します。皮膚は紫外線、乾燥、摩擦、大気汚染など、日常的に多様なストレスにさらされています。こうした刺激が続くと、炎症性メディエーター(サイトカインやプロスタグランジンなど)が過剰に分泌され、赤みやかゆみ、刺激感といった症状が現れます。さらに、角質層のバリア機能が低下すると外的刺激が侵入しやすくなり、炎症が慢性化する悪循環に陥ります。
このサイクルを断ち切るために、抗炎症成分を配合したスキンケアが注目されています。たとえばナイアシンアミドは、表皮細胞における酸化ストレス応答を抑制し、同時にセラミド合成を促進することでバリア機能の修復を支援することが知られています。また、ツボクサ由来の成分(マデカソシドやアジアチコシドなど)は、炎症性サイトカインの発現を抑え、抗酸化や鎮静効果を発揮することが報告されています。
つまり、抗炎症という概念は単なる「炎症を抑える」機能ではなく、皮膚の防御システムを健全に保つための包括的なアプローチであり、バリア機能の維持・修復と切り離せない関係にあります。
化粧品開発における抗炎症アプローチは、単独のテーマとしてではなく、他の機能性との組み合わせによって価値を高める戦略へと進化しています。美白やエイジングケアといった分野でも、炎症反応がメラニン生成やシワ形成の要因となることが明らかになり、抗炎症ケアがこれらの土台として位置付けられるようになっています。
また、抗炎症訴求を行う際には、科学的根拠の提示と広告表現の適正化が不可欠です。第三者機関による試験データの開示や、医薬部外品承認成分との整合性、公的ガイドラインに基づいた表現管理が、ブランドの信頼性を高める要素になります。さらに、サステナブルな原料調達や動物実験代替評価の導入など、環境・倫理面の取り組みを組み合わせることで、現代の消費者が求める「やさしさ」と「確かさ」を両立できます。
このように、抗炎症スキンケアの開発は、科学・倫理・市場の三方向からのバランスを取りながら進化しており、ブランドが長期的に支持されるための基盤づくりに直結しています。
肌の炎症を防ぐための成分には、「きちんと効くこと」と「安全に使えること」の両方が求められます。どちらか一方だけでは、安心して毎日使えるスキンケアにはなりません。
そこで、開発の現場では長く使われてきた国内承認成分をベースにしながら、新しい植物由来の素材や世界で注目される成分も取り入れる動きが広がっています。
ここでは、代表的な抗炎症成分とその働き、そして製品に取り入れるときの考え方を紹介します。
日本で古くから使われている代表的な抗炎症成分に、グリチルリチン酸ジカリウム(甘草由来)があります。医薬部外品の有効成分として認められており、ニキビや肌荒れ、赤みを防ぐ目的で多くの化粧水やクリームに配合されています。
この成分は「肌トラブルをやさしく鎮める」働きがあり、使用実績や安全性のデータも豊富です。製品の種類によって使える濃度の目安が異なり、洗い流すタイプ(洗顔料など)よりも肌に残るタイプ(乳液やクリームなど)では、より慎重に濃度を調整する必要があります。こうした基準が整っていることも、長年使われてきた理由のひとつです。
近年では、自然由来や多機能な成分への注目が高まっています。
たとえばナイアシンアミドは、ビタミンB3の一種で、肌のバリアを整える働きに加え、シミのもとになるメラニンの生成を抑えたり、乾燥やくすみを防いだりと、幅広い効果を持ちます。抗炎症成分としてだけでなく、美白やエイジングケアにも使える万能成分です。
また、ツボクサエキス(CICA)も人気が高まっています。ツボクサに含まれる「マデカソシド」や「アジアチコシド」という成分には、炎症を落ち着かせるほか、肌の修復や保湿を助ける働きがあります。韓国コスメで話題になりましたが、いまでは世界的に注目される鎮静成分のひとつになっています。
さらに、カミツレ(カモミール)やローズマリー、カンゾウ(甘草)など、昔から知られる植物エキスも、抽出技術の進歩によってより安定して使えるようになってきました。メーカーが自社の成分データを積極的に公開する流れもあり、「どんな試験をしてどんな結果が出たのか」を明示することで、より信頼性の高い製品づくりが進んでいます。
肌の炎症は、紫外線、乾燥、摩擦などの刺激によって起こります。これらの刺激が続くと、体の中で「プロスタグランジン」や「ヒスタミン」といった炎症を起こす物質が作られ、赤みやかゆみ、ほてりが出てきます。
グリチルリチン酸系の成分は、こうした炎症物質の発生を抑えることで、肌トラブルを静める作用があります。また、ヒアルロニダーゼという酵素の働きを弱めることで、アレルギー反応や刺激感を軽減する効果も知られています。
製品開発では、こうした成分を「どの段階で」「どの組み合わせで」使うかがポイントになります。たとえば、水分の多い化粧水ではすぐに肌に広がるように水溶性の成分を選び、乳液やクリームでは油に溶けやすいタイプを使うと効果的です。
さらに、セラミドなどの保湿・バリア成分を一緒に配合することで、肌の防御力を底上げし、炎症を起こしにくい状態に導くことができます。
抗炎症成分を配合するときには、「効かせすぎないこと」も大切です。実際には、こうした成分の多くは1%未満の低濃度で効果を発揮します。配合順やラベルの印字だけでは濃度が分かりにくいため、開発段階ではデータシートや試験結果を確認して慎重に設計する必要があります。
また、植物エキスの場合は抽出方法やpH(酸性・アルカリ性の度合い)、他の成分との相性によって安定性が変わります。成分を増やしすぎると刺激のリスクも上がるため、シンプルで相性の良い組み合わせを選ぶことがポイントです。
メーカーや原料会社が公開しているエビデンス(科学的根拠)も重要な判断材料になります。試験の種類(試験管内・肌上・臨床など)や評価方法を比較しながら、より信頼できるデータをもとに開発を進めることが、結果的に「安心して使えるスキンケア」を生み出す近道になります。
「抗炎症スキンケア」を名乗る製品をつくるためには、特定の有効成分を入れるだけでは十分ではありません。
大切なのは、処方全体のバランスで刺激をできるだけ減らし、肌のバリアを支える構造をつくることです。どんなに優れた成分を配合しても、界面活性剤や香料、アルコールなどが刺激源となってしまっては、本来の目的を果たせません。処方設計では、「守りながら効かせる」ことが重要な考え方になります。
マスク生活の長期化や季節の変化により、赤みや乾燥などのトラブルが起きやすい人が増えています。そうした肌に向けた製品では、エビデンス(科学的根拠)のある有効成分を使うことはもちろん、刺激をできるだけ抑えたベース設計が欠かせません。
特に重視されるのが、以下の3点です。
界面活性剤のマイルド化(洗浄力が強すぎないタイプを選ぶ)
溶媒(アルコールやグリコールなど)の刺激コントロール
保湿・エモリエント(油分)成分の層構造設計(肌のうるおいを逃がさないように重ねて守る)
最近の展示会や業界発表では、機能性と低刺激性、そして環境への配慮(サステナブル対応)を同時に満たす処方設計がトレンドとして取り上げられています。たとえば天然由来の乳化剤や、環境負荷の少ない保湿成分を採用しながら、使用感や効果を両立させる開発が進んでいます。
スキンケア製品を安定して効果的に仕上げるためには、「どのような形にするか(剤型)」の工夫が必要です。化粧水、乳液、ジェル、クリームなど、目的に合わせた設計を選ぶことで、成分の働きがより引き出されます。
また、有効成分を壊さず肌に届けるための技術も年々進化しています。
たとえば、
酸化しやすいビタミンCを安定させるために「誘導体化」する
成分をマイクロカプセルに閉じ込めて、ゆっくりと放出させる
油と水のバランス(相溶性)を最適化して浸透性を高める
といった方法があります。
こうした工夫は、高濃度ビタミンC製品やヒアルロン酸配合製品の開発でも使われており、「抗炎症×鎮静×保湿」を両立させる処方づくりにも応用されています。成分単体ではなく、「処方全体の調和」を考えることが、安定性と効果を両立するポイントです。
抗炎症スキンケアを製品化するうえで欠かせないのが、安全性と品質の確認です。
どんなに低刺激をうたっても、試験で実証できなければ信頼にはつながりません。
代表的な評価として、次のようなテストがあります。
48時間パッチテスト:肌に成分を貼って2日後に反応を見る方法。刺激やかぶれの有無を確認します。
アレルギーテスト:繰り返し使ってもアレルギー反応が出ないかを評価します。
敏感肌パネルテスト:実際に敏感肌の被験者で使用感や刺激をチェックします。
厚生労働省や関連機関のガイドラインでは、「RhE法」(再構築皮膚モデルを使う試験)と、実際の人の肌で行う連続刺激性試験を組み合わせて行う段階的な評価方法が推奨されています。こうした仕組みを活用することで、試験結果の妥当性や再現性が高まり、より確かな安全性を確認できます。
実際の開発現場では、外部の検査機関でパッチテストや使用試験を行い、「低刺激である」と客観的に示したうえで、表示ガイドラインに沿った表現を使います。これにより、消費者が安心して使える製品であることを明確に打ち出すことができます。
抗炎症スキンケアの開発は、単に「赤みを抑える」だけでなく、肌が本来もつ力を引き出すことを目指しています。
効果を裏づける科学的データを示すこと、そして安全で安心して使える処方を届けることの両立が、今の開発現場で最も重要なテーマです。ここでは、抗炎症製品の評価のしかたと、今後の市場の方向性を整理していきます。
「抗炎症効果がある」と言っても、その根拠をどう示すかが信頼を左右します。研究の現場では、まず細胞レベルの試験(in vitro)で、炎症性サイトカインと呼ばれる物質(IL-6、IL-8、TNF-αなど)がどの程度抑えられるかを調べます。これは肌が炎症を起こしたときに分泌される信号のようなもので、その減少が確認できれば、抗炎症効果の一つの証拠になります。
次の段階では、皮膚モデルや実際の人の肌での試験(in vivo)を行います。赤みの改善や水分量の回復などを、色差計や画像解析装置を使って客観的に測定する方法が一般的です。最近では、非侵襲(肌を傷つけない)測定技術が発達し、試験参加者への負担を抑えながら精度の高いデータを取得できるようになっています。
こうしたデータは、単に研究報告として終わらせるのではなく、製品のパッケージやブランドサイトなどで分かりやすく提示することで「信頼される根拠」へとつながります。消費者が実際に肌の変化を感じ、その体感を数字で裏付けられる製品こそが、今後の市場で支持を得るでしょう。
抗炎症をテーマにしたスキンケアでは、「低刺激」や「敏感肌対応」といった表現もよく使われますが、これらには明確な根拠が求められます。
厚生労働省や日本化粧品工業連合会のガイドラインでは、安全性を確認するために複数の試験を行うことが推奨されています。代表的なのは、48時間パッチテスト(肌に塗布してかぶれが出ないか確認する方法)やアレルギーテスト、敏感肌パネル試験(敏感肌の人を対象にした使用感テスト)などです。
また、表示表現にも注意が必要です。「炎症を抑える」「かゆみを治す」といった表現は医薬品的とみなされる場合があり、化粧品では「肌荒れを防ぐ」「肌をすこやかに保つ」といった表現にとどめることが求められます。
海外でも同様の基準が整備されており、特に欧州では「データのない効果主張」に対する監視が強化されています。こうした背景から、日本企業も海外展開を見据えて自社基準の明確化や第三者機関でのデータ取得を進める動きが広がっています。
抗炎症という概念は、いまやスキンケアの“土台”として定着しつつあります。最近では、他の機能と組み合わせた多面的な処方が注目されています。
たとえば「抗炎症×美白」では、紫外線刺激による炎症がメラニン生成を促進することに着目し、ナイアシンアミドやCICAを組み合わせた肌色均一ケアが登場しています。「抗炎症×エイジングケア」では、慢性的な炎症(いわゆる“サイレントインフラメーション”)がシワやハリ低下の要因になることから、抗酸化・鎮静作用を持つ植物エキスやペプチドが注目されています。
さらに、「抗炎症×マイクロバイオーム(皮膚常在菌バランス)」という新しい視点も登場しました。肌のバリアを守る善玉菌の働きを整え、炎症を起こしにくい環境をつくるという考え方です。乳酸菌由来成分や発酵エキスなどがこれに活用されています。
同時に、サステナブルな成分選びも欠かせない要素となりました。環境に配慮した抽出方法や再生可能な植物原料、リサイクル容器を採用することで、消費者の共感を得やすくなっています。抗炎症はもはや“機能”だけでなく、“やさしさ”や“倫理性”を表すキーワードにもなりつつあります。
矢野経済研究所の調査によると、国内の敏感肌・低刺激性化粧品市場は今後も年率5〜6%の成長が見込まれています。背景には、花粉・乾燥・マスク摩擦などの外的刺激に敏感な生活環境の広がりがあります。また、男性や若年層にも「肌のゆらぎ」を感じる層が増え、性別・年齢を問わないスキンケア需要が高まっています。
海外に目を向けると、欧州では「dermo-cosmetics(皮膚科学発想の化粧品)」が急速に伸びています。ラ・ロッシュ・ポゼやアベンヌといったブランドが象徴的で、皮膚科医監修の製品やアレルギーテスト済み製品が支持を集めています。北米ではクリーンビューティ市場と融合し、「炎症を抑えながら肌を整える」という考え方が主流になりつつあります。
今後の国内市場では、医薬部外品の開発強化やAIを活用した肌解析、マイクロバイオーム研究との連携が進むとみられます。特にAI解析では、個人の肌状態に合わせて「炎症リスク」を予測し、最適な成分組み合わせを提案する技術が研究段階から実用化へと移行しています。
抗炎症ケアは、もはや特定の肌質だけでなく「すべての肌を健やかに保つ」ための基本概念として拡大していくでしょう。
肌の赤みや刺激を防ぎたいというニーズが高まる中、「抗炎症スキンケア」は今や化粧品開発の中心テーマになっています。マスク生活や環境ストレスで肌が敏感になりやすい時代に、ただ炎症を抑えるだけでなく、肌を守りながら健やかに整える処方設計が求められています。
注目される成分は、グリチルリチン酸ジカリウムやナイアシンアミド、ツボクサエキスなど、科学的根拠と安全性を両立したものです。これらをバランスよく組み合わせ、界面活性剤や保湿成分の設計を工夫することで、低刺激で効果の高い処方が実現できます。また、パッチテストやアレルギーテストなどの安全性評価を丁寧に行い、エビデンスに基づいた製品づくりを進めることが信頼を生みます。
抗炎症スキンケアは、これからの市場において“やさしさ”と“確かさ”を象徴するカテゴリーとして成長が期待されています。
株式会社OEMでは、エビデンスに基づく処方開発から薬機対応、製品化までを一貫してサポートしています。抗炎症スキンケアの企画・開発をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

セラミド配合スキンケアをOEMで開発する完全ガイド|種類・処方・メーカー選びまで
2026.1.28
インナーケアブランド立ち上げ完全ガイド|市場動向からOEM活用、成功のポイントまで
2025.12.25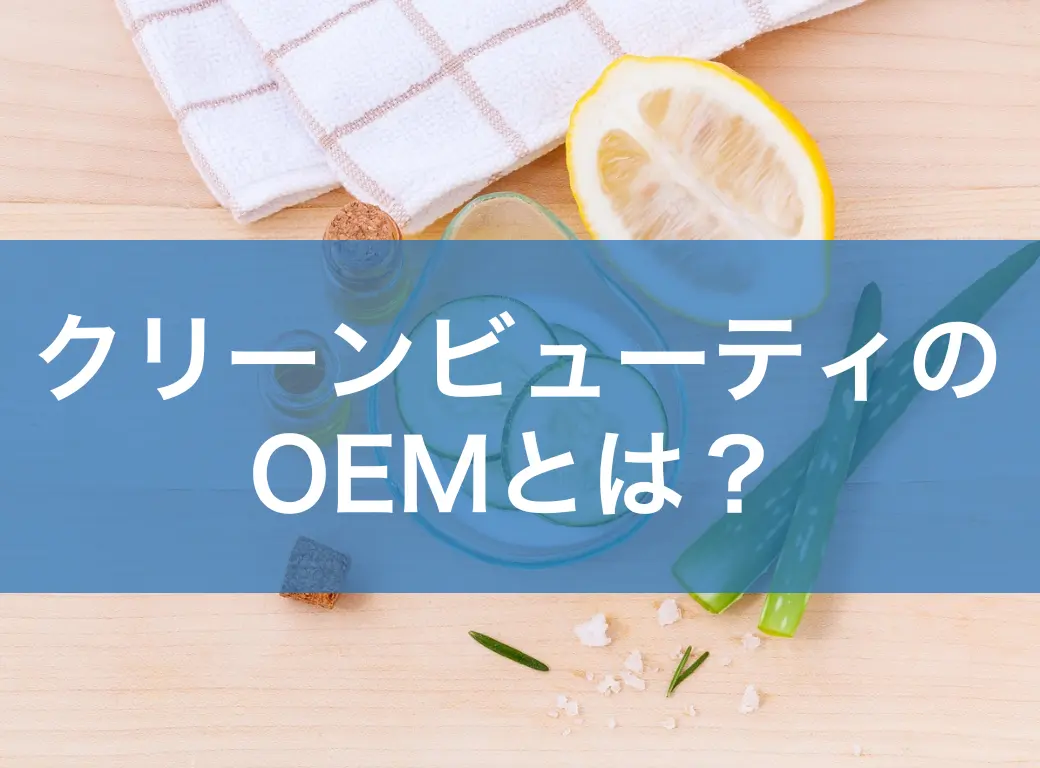
クリーンビューティのOEMとは?定義・課題・メーカー選びまで徹底解説
2025.12.24お問い合わせはこちらまで