
- HOME
- 化粧品OEMラボ
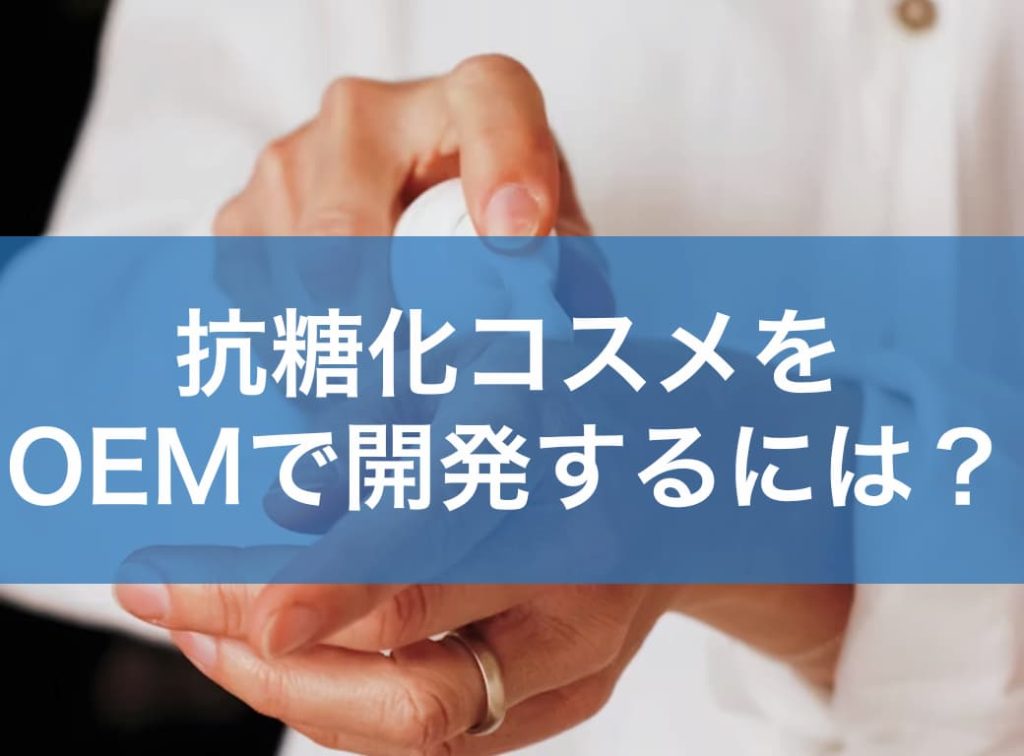
近年、スキンケア領域で「糖化(Glycation)」というキーワードが注目を集めています。肌内部で糖とたんぱく質・脂質が結びついて生成される「終末糖化産物(AGEs:Advanced Glycation End Products)」は、黄ぐすみ・ハリ低下・弾力喪失などのエイジングサインと密接な関係があることが明らかになっています。
こうした背景を受け、OEM(Original Equipment Manufacturer)・ODM(Original Design Manufacturer)企業やブランドのR&D部門では、「抗糖化」を訴求軸とした化粧品開発への関心が高まっています。
本記事では、R&D・OEM担当者に向けて「機能性」「差別化」「実装性」の3軸から抗糖化化粧品OEMを成功に導くポイントを整理します。
年齢を重ねるにつれて現れる肌のくすみや弾力低下。その一因として注目されているのが「糖化」という現象です。糖化は酸化と並び、肌老化の主要な要因とされており、化粧品開発の現場でも「抗糖化ケア」は新しいアンチエイジング戦略として注目を集めています。
糖化とは、体内で余分な糖がタンパク質や脂質と非酵素的に結びつき、反応が進行することで「AGEs(終末糖化産物)」を生成する現象を指します。皮膚でも同様の反応が起こり、角層や真皮に存在するコラーゲンやエラスチンが糖化によって硬化・変性します。その結果、肌の弾力が失われ、たるみや黄ぐすみといった老化サインが現れやすくなります。
花王の研究によると、角層中の蛍光性AGEs量と肌の黄み度には有意な相関があることが確認されており、糖化が肌トーンに直接的な影響を及ぼすことが明らかになっています(週刊粧業オンライン参照)。さらに、糖化は酸化ストレスや紫外線ダメージとも関連が深く、抗酸化対策と並行して「抗糖化」の視点を組み込むことが、今後の製品開発ではより重要になると考えられます。
糖化の進行は、肌の外見や質感にさまざまな悪影響をもたらします。具体的には、以下のような変化が起こることが報告されています。
肌が黄色くくすんで見える(黄ぐすみ)
ハリや弾力が失われ、しぼんだような印象になる
角層の水分保持力が低下し、キメが乱れてざらつきが出る
コラーゲンやエラスチンの構造が硬化し、シワやたるみが進行する
このような変化を抑える抗糖化ケアは、「糖化ケア=次世代アンチエイジング」として美容業界で存在感を高めています。近年では、「透明感アップ」「黄ぐすみ対策」「糖化ケア成分配合」といった訴求ワードを掲げた製品がOEM市場でも増加傾向にあります。
抗糖化化粧品の価値を高めるためには、科学的根拠に基づいた有効成分の選定が欠かせません。「どのような成分がAGEsの生成を抑え、肌の糖化を防ぐのか」という問いに対しては、植物由来エキスを中心とした多様な研究報告が蓄積されています。
ここでは、代表的な抗糖化成分と、開発担当者が押さえておきたい処方設計上のポイントを整理します。
近年の研究や原料メーカーの開発動向を見ると、抗糖化機能を有する成分として以下のような例が挙げられます。いずれも、植物が本来持つ防御機構や抗酸化力を応用したものであり、化粧品への応用が進んでいます。
まず注目されているのが、セイヨウオオバコ種子エキス由来の「プランタゴサイド」です。
イチマルファインケミカル株式会社の研究では、プランタゴサイドが糖とタンパク質の結合を抑制し、AGEsの生成を防ぐ作用を示すことが報告されています。この成分は植物由来でありながら高い機能性を持ち、マイルドな処方設計にも適しています。
また、茶実エキス、ハマナス花果実エキス、和栗渋皮エキスといった植物エキスにも、糖化抑制と透明感向上の両面での効果が期待されています。
サティス製薬の研究では、これらの天然エキスが肌のくすみ軽減と明度向上に寄与することが示唆されており、ブランド訴求においても「植物由来」「サステナブル原料」という切り口で支持を得ています。
さらに、植物エキス混合物を用いた角層中AGEs低減実験では、2週間の使用で蛍光性AGEs量が有意に減少したという報告もあります(週刊粧業オンライン)。この結果は、化粧品による抗糖化ケアが肌表面レベルで実証可能であることを示しており、今後のR&Dにおける指標としても注目されています。
こうしたエビデンスの積み重ねにより、抗糖化成分は単なる「トレンドワード」ではなく、科学的根拠を持つ機能性原料として確立しつつあります。
抗糖化成分を製品に応用する際には、研究開発者が慎重に検討すべき要素がいくつかあります。
どれほど優れた機能を持つ成分であっても、配合設計を誤ると期待する効果を発揮できないため、処方設計上の最適化が求められます。
まず重要なのが成分の安定性です。糖化抑制機能を有する多くの植物エキスは、光や熱、pH変化に影響を受けやすい傾向があります。安定性試験や保存条件の検証を行い、活性を維持できるベース処方を構築することが必要です。
次に、有効濃度と臨床データの提示が信頼性の鍵となります。糖化ケアを訴求する場合には、AGEs生成抑制率や角層中AGEs低減効果など、定量的なデータをもとに説明することが望まれます。たとえば、植物エキス混合物の使用によってAGEs生成を約63%抑制したという実験報告が紹介されています。こうしたデータを持つ原料を選定することで、OEM先への提案力が高まります。
さらに、製剤形態の選定も開発戦略を左右します。抗糖化成分は化粧水や美容液、クリームなどのスキンケア製品に加え、ドリンクやサプリメントなどのインナーケア領域にも応用が広がっています。
また近年では、「エクソソーム産生×W抗糖化」といった複合アプローチで差別化を図る提案も登場しており、抗糖化テーマの広がりを示しています。
抗糖化は今や、敏感肌・美白・アンチエイジングに続く次世代のスキンケアテーマとして、OEM市場でも注目度が高まっています。
しかし、ブランドへの提案段階では、成分エビデンスだけでなく、薬機法への適合、表現設計、差別化軸、実装性といった複合的な観点が求められます。
ここでは、抗糖化テーマを開発・提案する際に押さえておくべき実務上のポイントを整理します。
OEM企業がブランドに抗糖化製品を提案する際、まず重要になるのが訴求表現の適正化です。
「糖化を防ぐ」「AGEsを生成させない」などの科学的表現は、医薬品的効能を連想させるおそれがあるため、薬機法上は注意が必要です。化粧品の範囲内で許容される表現かどうかを十分に確認し、必要に応じてエビデンス資料や社内チェック体制を整備しておくことが求められます。
そのうえで、消費者に伝わりやすい言葉を選ぶことも大切です。「黄ぐすみケア」「ハリ不足対策」「糖化ケア対応」「透明感サポート」といった表現は、法的に安全でありながらブランド訴求力も高い表現として活用できます。
また、エビデンスの有無を明確にしておくことで、営業資料やブランドサイトでの信頼性を高めることができます。
さらに、近年では「糖化」というキーワードに対する消費者の理解が徐々に進みつつあり、この認識変化を踏まえた情報共有が重要です。ブランドと共同で訴求コンセプトを設計することで、マーケティング面でも整合性のある製品開発が実現します。
抗糖化というテーマ自体が市場で広がりを見せるなかで、OEM・ブランド双方が競合との差別化を図るためには、成分・機能・製剤の三軸で戦略を立てる必要があります。
まず、原料による差別化が効果的です。希少な植物エキスや国産素材、発酵由来成分などを活用することで、製品のストーリー性を高められます。
和栗渋皮エキスや茶実エキスなど、日本独自の植物資源を活かした抗糖化原料の開発を進めています。これにより、地域性やサステナビリティを兼ね備えた製品設計が可能になります。
次に、機能の掛け合わせによる価値創出も有効です。抗糖化と抗酸化、抗糖化とエクソソーム活性、抗糖化と保湿強化といった複合機能を打ち出すことで、ワンテーマ製品との差別化が図れます。
さらに、製剤・剤型による展開の幅も差別化要素となります。スキンケア(化粧水・美容液・クリーム)に加えて、ドリンク型やサプリメント型の“飲む美容”製品、あるいはヘアケアやボディケア領域への応用など、用途の拡張によってブランドポートフォリオを強化できます。これらの方向性を踏まえた多角的な製品ライン提案を行うことで、ブランドの成長戦略に寄与できます。
抗糖化をテーマにした化粧品開発では、コンセプト設計から処方検討、試作、エビデンス取得、量産まで一連の流れを戦略的に設計することが成功の鍵になります。OEM企業と連携しながら、研究開発とマーケティングの視点を両立させるプロセスが求められます。
まず、ターゲット層と訴求軸を明確にします。
抗糖化は「黄ぐすみ・ハリ・弾力低下」といったエイジングサインに訴求できるテーマのため、アンチエイジングや美白、透明感ラインと親和性が高いカテゴリーです。
競合調査やトレンド分析を通じて、「抗酸化+抗糖化」などの複合アプローチを検討する企業も増えています。
次に、糖化抑制効果やAGEs生成抑制に関する科学的データを持つ原料を選定します。
代表的な抗糖化成分には、カルノシン、アルジルリン酸、ルイボスエキス、ハス胚芽エキスなどがあります。
OEM企業によっては、独自の抗糖化原料や特許技術を提案できるケースもあり、他社との差別化ポイントになります。
選定した成分の安定性や配合バランスを確認しながら、処方開発を行います。
抗糖化成分は熱や光、pHに敏感なものも多いため、乳化方法や溶解順序の工夫が重要になります。
試作段階では、抗糖化訴求を実感できる使用感(なめらかさ、ツヤ、ハリ感)も同時に検証します。
完成した処方について、in vitro試験やヒト実験などを通じて機能性を確認します。
OEMメーカーの多くは外部試験機関とのネットワークを持ち、AGEs生成抑制試験や蛍光強度測定などのサポートを行っています。
データの裏付けを得ることで、訴求根拠を強化できます。
抗糖化化粧品は、機能性だけでなく「エイジングケア×上質感」を演出するデザインが重視されます。
内容物との相性(耐光性・密閉性)を考慮しながら、ガラスボトルやエアレス容器など適した仕様を選定します。
量産段階では、スケールアップ時の安定性確認、品質管理、薬機法に基づく表示チェックが行われます。
OEMメーカーは製造記録や成分証明書の発行など、監査・申請に必要なドキュメント対応を一貫して行います。
製品完成後は、OEMメーカーによる販売サポートや販促ツール制作の支援を受けることも可能です。「糖化×透明感」「抗糖化×抗酸化」といったメッセージを中心に、ブランドストーリーを強化していきます。
本稿では、肌内部で進行する糖化のメカニズムと、それを抑える「抗糖化ケア」の意義を、科学的根拠と実務の両面から整理しました。糖とタンパク質の結合によって生成されるAGEsは、コラーゲンやエラスチンの硬化を引き起こし、黄ぐすみやハリの低下を招く要因とされています。こうした糖化ダメージを軽減することは、これまで抗酸化ケアではカバーしきれなかった領域に新たな価値を生み出す取り組みです。
研究の進展により、セイヨウオオバコ種子エキス由来のプランタゴサイドや、茶実・ハマナス・和栗渋皮といった植物エキスの抗糖化作用が注目されています。
これらの原料は透明感やハリの改善など、実際の肌変化を裏付けるエビデンスが得られており、OEM/ODM製品の差別化にもつながります。製剤設計の段階では、成分の安定性・有効濃度・ベース選定を慎重に行うことが信頼性を高める鍵となります。
一方で、製品化においては薬機法対応を踏まえた表現設計が欠かせません。「糖化を防ぐ」などの直接的な言い回しを避け、「黄ぐすみケア」「ハリ不足対策」「糖化ケア対応」といった消費者に分かりやすく、法的に適正な表現を選ぶことが重要です。
株式会社OEMでは、抗糖化・抗酸化・エクソソーム・発酵由来原料など、機能性と差別化を両立する化粧品開発を幅広くサポートしています。処方提案から薬機法チェック、量産・納品体制まで一貫したサポートが可能です。
次世代スキンケアとしての「抗糖化」をブランドの強みとして打ち出したい方は、ぜひ一度株式会社OEMまでお問い合わせください。

セラミド配合スキンケアをOEMで開発する完全ガイド|種類・処方・メーカー選びまで
2026.1.28
インナーケアブランド立ち上げ完全ガイド|市場動向からOEM活用、成功のポイントまで
2025.12.25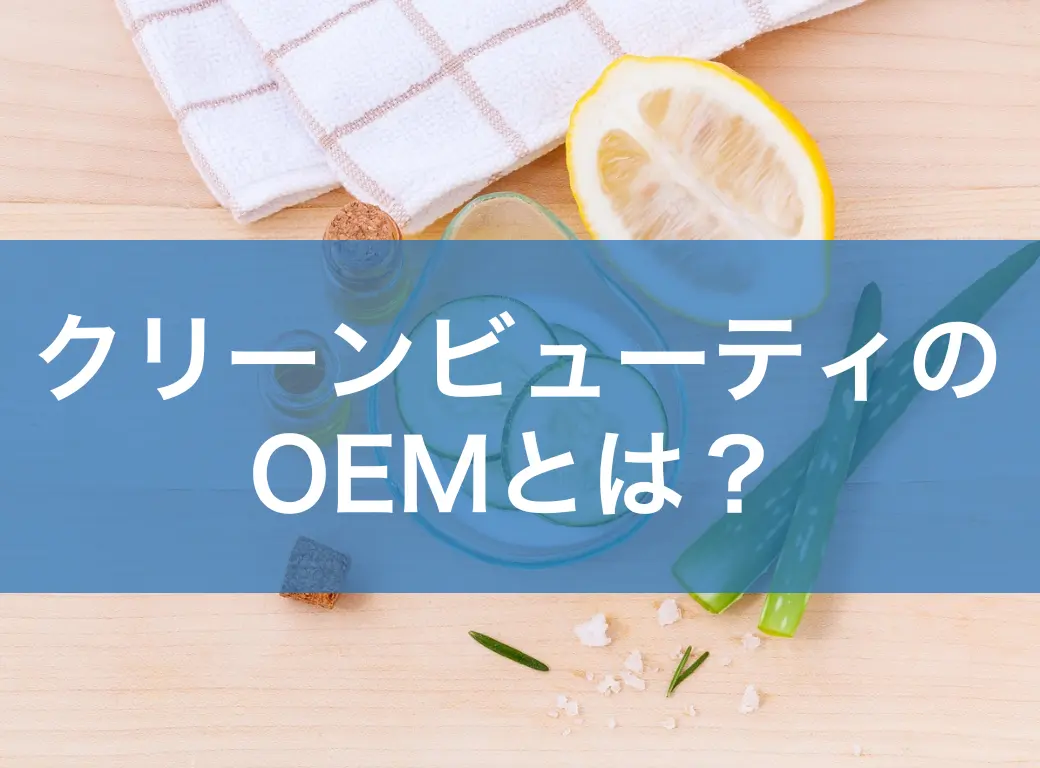
クリーンビューティのOEMとは?定義・課題・メーカー選びまで徹底解説
2025.12.24お問い合わせはこちらまで