
- HOME
- 化粧品OEMラボ

化粧品市場では「肌に優しい」「安心して使える」という価値が強く求められています。その中でも香料を加えない無香料化粧品は、敏感肌や香りに敏感な消費者を中心に需要が高まっています。しかし自社で一から無香料化粧品を製造するのはハードルが高いため、多くの企業がOEMメーカーに委託して商品を展開しています。
本記事では無香料化粧品の特徴やOEM活用のポイントを解説し、ブランド展開の実務に役立つ知識を整理します。
Contents
無香料化粧品とは、合成香料や天然香料といった香り成分を配合していない製品を指します。全くの無臭という意味ではなく、原料そのものが持つ匂いは残ることがあります。
一方で「微香性」は香料を少量配合して匂いをマイルドに抑えている製品です。消費者にとっては「無香料」と「微香性」の違いが分かりづらいため、明確な表示や説明が重要になります。
無香料処方を選択することには、いくつかの明確な利点があります。まず第一に、香料による刺激やアレルギー反応の懸念が少ないため、敏感肌やアレルギー体質の人々でも安心して使用できるという点が挙げられます。さらに、香りの好みに左右されにくいため、性別や年齢を問わず幅広い層に受け入れられやすく、市場での訴求力が高まります。
また、法規制の観点からも無香料は優位に立ちやすい存在です。近年は薬機法や海外規制において香料成分への制約が強まっており、リスク回避やスムーズな海外展開を実現しやすくなっています。加えて、「シンプルケア」や「クリーンビューティー」といったコンセプトと相性がよく、ブランドイメージを明確に訴求できる点も重要なメリットです。こうした背景から、無香料は機能性とマーケティングの両面で注目度を高めています。
一方で、無香料処方にはいくつかの課題が伴います。香料が加わらない分、製品中の原料が持つ独特の匂いを隠すことが難しく、使用感に影響を及ぼす場合があります。香りの演出は単なる嗜好性だけでなく、使用後の満足感にも直結するため、官能評価の低下につながる可能性があります。
さらに、香料にはときに抗菌作用や安定性の補助といった機能的役割もあるため、それを取り除くことで保存性に課題が生じることもあります。そのため、安定剤や防腐剤を適切に組み合わせる技術が不可欠です。また、香りが目立たない高品質の原料を選定する必要があり、原料調達の自由度が下がることでコストが上昇するリスクも考えられます。
このように、無香料化粧品はメリットとリスクの両面を持ち合わせています。消費者が安心して使える製品を届けるためには、処方設計や原料選びにおいて、メリットを活かしながら課題をどう克服するかが鍵となります。
無香料化粧品の開発では、通常のスキンケア製品よりも高い専門性が求められます。香料を使わない分、原料の匂いを抑える工夫や保存性の確保が欠かせず、OEM工場の技術力や対応力が商品力を左右します。そこで、どのような観点で工場を選ぶべきかを整理します。
まず確認したいのは、無香料処方の開発経験を持つかどうかです。香料を使わない場合、原料選びや処方の工夫で匂いを抑える必要があります。そのため、原料調達の幅が広く、匂いを最小限に抑える独自技術を備えた工場は大きな強みを持っています。
香料はときに抗菌や安定化の役割を果たします。その代替手段を持たないと、無香料化粧品の保存性や使用感に課題が残ります。防腐剤や安定化技術に関する知識が豊富で、品質試験の体制が整っている工場であれば、安定した製品供給が可能になります。
無香料化粧品は国内市場だけでなく、海外展開を意識するブランドも多い分野です。EUやアメリカでは香料成分に厳しい規制があるため、国際的な法規制を熟知した工場であるかを確認することが重要です。さらに、GMPやISOといった品質認証を取得しているかどうかは、信頼性を見極める基準となります。
新規ブランドや新ラインの立ち上げでは、試作を重ねて官能評価を行う工程が欠かせません。そのため、小ロット生産や柔軟なサンプル提供に対応できる工場は心強い存在です。さらに、テストマーケティングから本格的な量産へとスムーズに移行できる体制を持っているかどうかも大切な判断材料になります。
最後に、単なる受託先ではなく、ブランドの成長を共に支えるパートナーとなれるかどうかが重要です。製造能力だけでなく、企画やマーケティングの視点からも相談できるOEM工場は、長期的な事業拡大に大きく貢献します。
無香料化粧品を商品化するプロセスは、一般的な化粧品のOEMと共通する部分もありますが、香料を使わないことによる特有の工夫や注意点が存在します。以下では、企画から市場投入までの流れを段階的に整理します。
開発の第一歩はコンセプトの明確化です。ターゲットとなる顧客層やブランドイメージを踏まえ、無香料であることの価値をどう打ち出すかを設計します。例えば「敏感肌向け」「クリーンビューティー」「海外規制対応」といった切り口が考えられます。この段階で香料を使わないことによる課題をどう克服するか、処方方針を定めることが重要です。
香料を加えない場合、原料自体の匂いが前面に出やすくなります。そのため、香りが少ない原料の調達や、原料由来の匂いを抑えるマスキング技術の活用が必要です。また、防腐剤や安定剤を適切に組み合わせることで、保存性や安定性を確保しながら「無香料」の品質を守ります。
試作品の段階では、匂いだけでなく、使用感やテクスチャーを含む官能評価が欠かせません。香料による快適さがない分、肌へのなじみやすさや塗布後の感触が評価の中心になります。サンプルを何度も改良し、使用テストを通じて顧客が満足できる品質を作り込む工程が求められます。
処方が確定した後は、量産に向けたスケールアップを行います。無香料化粧品では、原料の匂いがロットによって微妙に変化することがあるため、ロット管理と品質保証体制を厳密に整える必要があります。さらに、異物混入を防ぐための衛生基準やクリーンルームでの製造体制を確立することも欠かせません。
最終段階では、パッケージやラベルの表示設計を行います。「無香料」と表記する場合は、薬機法や各国の規制に準拠し、誤解を招かない成分表示を徹底する必要があります。例えば「香料不使用」と「微香性」の違いを明確に示すことで、消費者の信頼を得ることができます。
無香料化粧品は、敏感肌対応や法規制順守といった観点から需要が高まっており、ブランド戦略としても「シンプル」「クリーンビューティー」といった価値を強く訴求できる存在です。しかし同時に、原料由来の匂いを抑える工夫や保存性の確保といった課題があり、開発から製造までのプロセスでは高度な専門性が求められます。
OEM工場の選定においては、無香料処方の実績や原料調達力、規制対応の知見、品質保証体制などを総合的に見極めることが不可欠です。また、コンセプト設計から試作、スケールアップ、表示設計に至るまで、各工程でブランド側と工場が綿密に連携することが、最終的な商品力を左右します。
無香料化粧品のOEMは決して容易ではありませんが、適切なパートナー選びと計画的なプロセス管理によって、消費者の信頼を得られる高品質な製品を生み出すことができます。これからの市場においては、無香料であることが単なる差別化ではなく、持続的なブランド価値を築く重要な要素となっていくでしょう。

セラミド配合スキンケアをOEMで開発する完全ガイド|種類・処方・メーカー選びまで
2026.1.28
インナーケアブランド立ち上げ完全ガイド|市場動向からOEM活用、成功のポイントまで
2025.12.25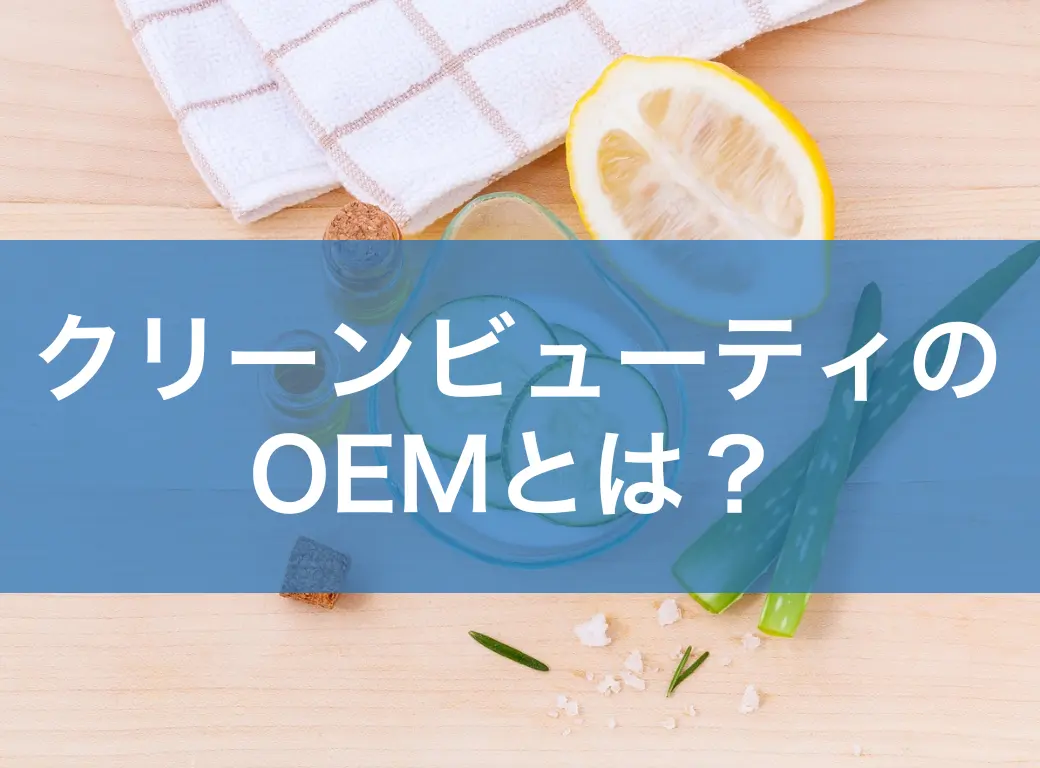
クリーンビューティのOEMとは?定義・課題・メーカー選びまで徹底解説
2025.12.24お問い合わせはこちらまで